| 2025年8月のみことば |
| イエスは、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、弟子たちにたとえを話された。 「ある町に、神を畏れず人を人とも思わない裁判官がいた。
ところが、その町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては、『相手を裁いて、わたしを守ってください』と言っていた。 裁判官は、しばらくの間は取り合おうとしなかった。しかし、その後に考えた。『自分は神など畏れないし、人を人とも思わない。
しかし、あのやもめは、うるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやって来て、わたしをさんざんな目に遭わすにちがいない。』」
それから、主は言われた。「この不正な裁判官の言いぐさを聞きなさい。 まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでもほうっておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうか。」 (ルカによる福音書18章1~8節) |
 ルカ福音書は、ここから18章になります。章が変わったことで、前の17章とはお話が変わるのではないかと思ってしまいそうですが、今日のたとえは、特に17章から繋がっているお話です。皆さんも何度か読まれたことがあると思います。1人のやもめが、不正な裁判官に対して、裁判を起こしたいとしつこくお願いを続けます。すると、その裁判官は根負けし、やもめの願い通りに裁判をするというたとえ話です。 ルカ福音書は、ここから18章になります。章が変わったことで、前の17章とはお話が変わるのではないかと思ってしまいそうですが、今日のたとえは、特に17章から繋がっているお話です。皆さんも何度か読まれたことがあると思います。1人のやもめが、不正な裁判官に対して、裁判を起こしたいとしつこくお願いを続けます。すると、その裁判官は根負けし、やもめの願い通りに裁判をするというたとえ話です。この部分だけを読んだら、絶えず祈ることが大切なのだという教えのたとえだと読みがちです。イエス様は、すでにルカ11章5~13節で、諦めずに祈り続けることが大切だということを教えてくださいました。それは次の様なものでした。イエス様は、真夜中に友達がパンを3つ貸してほしいと頼みにくるたとえから、祈りそのものについて教えてくださいました。「友達ということでは起きて何か与えるようなことはなくても、しつように頼めば、起きて来て必要なものは何でも与えるであろう。だれでも、求める者は受け、探す者は見つけ、門をたたく者には開かれる。天の父は求める者に必要なものを、聖霊を与えてくださる」と。 今日の教えは、それと似ているようでちょっと違います。今日のお話は、「神の国はすでにあり、人の子はやがて来る」という文脈の中で語られています。神の国は、今すでにイエス様が地上に来られて始まっています。神の国とは、神の子イエス様が王として支配してくださる国であり、イエス様と共に生きる時と所ですでに始まっているのです。けれども、まだ完成はしていません。今日の教えは、「すでに」と「未だ」のはざまの時代にあって、人の子イエス様が再び来られるという主の再臨が意識されています。実際、今日の8節でも、イエス様は人の子の再臨について言及しています。 イエス様は普段、おもむろにたとえを語り始めますが、今日は、最初にたとえの目的を伝えています。1節、「気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために」と。「気を落とさずに」は「失望せずに」ということです。イエス様は弟子たちが失望しないために、そして、絶えず祈らねばならないことを教えるために、今日のたとえを話されます。弟子たちは、今後、迫害の困難の時代を歩んでいくからです。イエス様ご自身、このたとえを話しておられる時点で、十字架への歩みの途上にあり、すでにユダヤ教の指導者たちからは目をつけられています。そして今後、イエス様が殺された後は、弟子たちへ迫害の手がのびていきます。 イエス様を、また弟子たちを迫害しようとする人たちは、神の民とされている人たちです。神の民イスラエルは、旧約時代から預言されている人の子・メシア・キリストの到来を待ち望んでいましたが、この世は、神が遣わす「人の子」がイエス様であるということを、信じる者と信じない者とに分かれています。裁きの日には、信じる者と信じない者がどうなるのかが、17章34節以下で教えられました。「言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に臼をひいていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。」 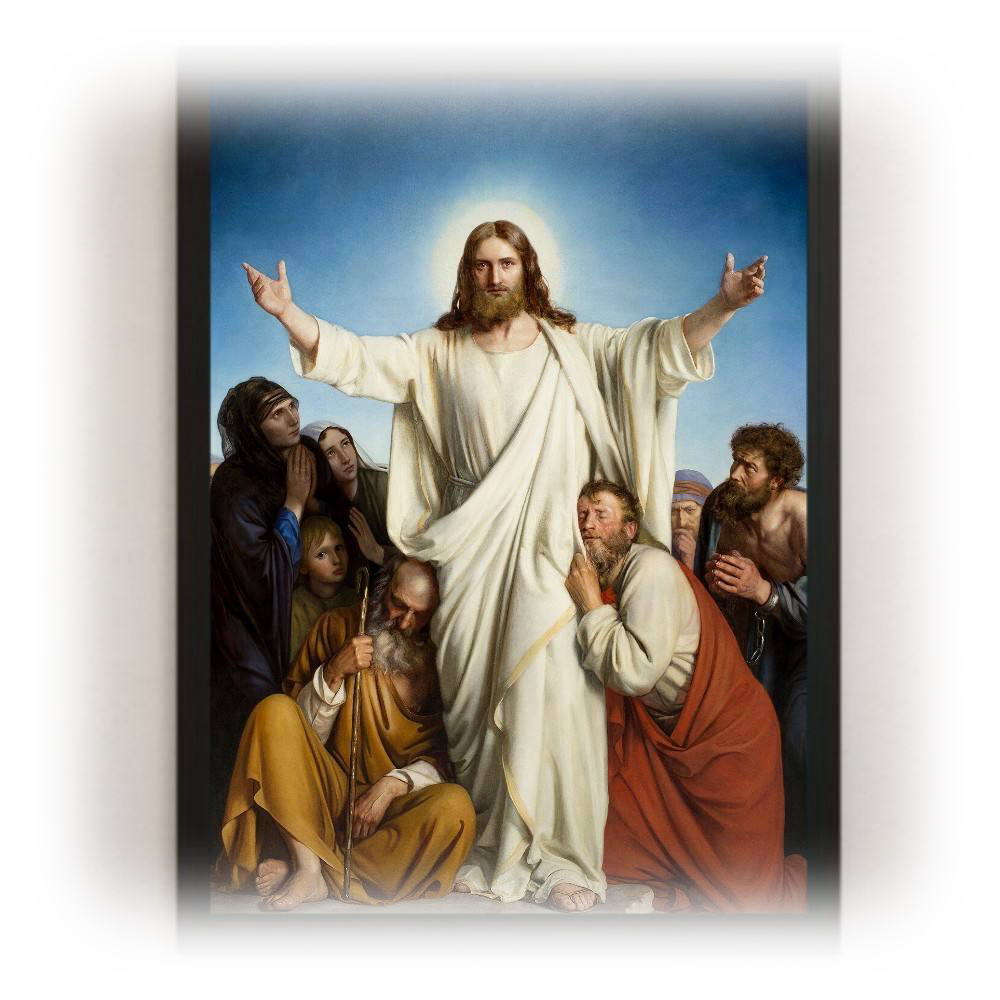 神様は、全ての人が、イエス様こそが救い主であると告白し、救われて、神の国が広がっていくことを望んでおられますが、この世は、まだまだその途上にあります。神の国はすでに始まっていますが、まだ完成していません。神に背き、神を畏れない人たちが溢れ、悪がはびこっています。弟子たちも人々も、神のご支配は本当に来るのだろうか、いつになったら悪が正しく裁かれる時が来るだろうかと、人の子・救い主・キリストが待ち望まれていた時代です。イエス様は、そんな時代を生きている人々へ、また特に、迫害に遭うであろう弟子たちへ、失望しないように、絶えず祈るようにと、2~5節でたとえを語ります。 神様は、全ての人が、イエス様こそが救い主であると告白し、救われて、神の国が広がっていくことを望んでおられますが、この世は、まだまだその途上にあります。神の国はすでに始まっていますが、まだ完成していません。神に背き、神を畏れない人たちが溢れ、悪がはびこっています。弟子たちも人々も、神のご支配は本当に来るのだろうか、いつになったら悪が正しく裁かれる時が来るだろうかと、人の子・救い主・キリストが待ち望まれていた時代です。イエス様は、そんな時代を生きている人々へ、また特に、迫害に遭うであろう弟子たちへ、失望しないように、絶えず祈るようにと、2~5節でたとえを語ります。ある町に、神を畏れず人を人とも思わない裁判官と、一人のやもめがいました。6節でイエス様は、この裁判官のことを「不正な」と言っていますが、このような裁判官は、当時多くいたようです。本来、裁判とは、正義を明らかにするものですが、当時のイスラエルでは、公正であるべき裁判官が、自分の利益のためにわいろを要求したりして、不正な裁判を行なっていたことも少なくなかったようです。 そして、やもめについて、旧約聖書には守られるべき存在であることが記されています。申命記10章18節 「孤児と寡婦(やもめ)の権利(裁き、裁判)を守り」、申命記27章19節 「寄留者、孤児、寡婦(やもめ)の権利をゆがめる者は呪われる」などとあります。また、出エジプト22章21~23節 「寡婦や孤児はすべて苦しめてはならない。もし、あなたが彼を苦しめ、彼がわたしに向かって叫ぶ場合は、わたしは必ずその叫びを聞く」ともあります。けれども、今日のたとえに登場するやもめは、いえ、彼女だけでなく、おそらく多くのやもめは、弱い立場に置かれ、生活も苦しかったでしょう。本来、裁判官は、このようなやもめのために、神の御心に従って、正しい裁判をする義務があるのですが…。 たとえのやもめは、何か彼女を苦しめるものがあったのでしょう。でも、具体的に何を訴えているのか、それは記されていません。やもめは裁判官のところに来ては、「相手を裁いて、わたしを守ってください」と訴えました。でも、この裁判官は、「神を畏れず、人を人とも思わない」とあるように、やもめの訴えに取り合おうとしません。けれども、その後に考えました。「自分は神など畏れないし、人を人とも思わない。しかし、あのやもめは、うるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないと、ひっきりなしにやって来て、わたしをさんざんな目に遭わすにちがいない」と。彼は自分で自分のことを、神のことも人のことも思わない人物だと認識しています。神のことも人のことも思わないで何を思っているかというと、自分のことだけなのでしょう。何度もやってくるやもめがうるさくてかなわない。散々な目に遭わされたくない。 ところで、「散々な目に遭わす(ὑpωpιάζw=殴る、うち叩く、悩ます、苦しめる)」と訳されている語が面白い言葉なのですが、「目の下に隈ができるようなことをされる」という言葉です。彼女がひっきりなしにやってくるから、ストレスが溜まるような…。あるいは、訴えても訴えても聞こうとしない無情な裁判官に対して、いつか彼女は彼の顔を目掛けて殴りかかってくるような…。そうしたら、本当に目の下に隈ができる。精神的にも肉体的にも痛めつけられそうだ。そんなことになるくらいなら、しょうがない、裁判をするか…、と考えたようです。彼は、やもめのしつこさに打ちのめされ、訴えを受け入れ、裁判をすることにしました。ここまでがたとえです。 イエス様は教えてくださいます。6~7節、「この不正な裁判官の言いぐさを聞きなさい。まして神は、昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでもほうっておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。」ここでイエス様は、不正な裁判官と、神様を対比させています。不正な裁判官と、正義の神です。不正な裁判官でさえ、うるさく求める人の訴えを聞くのであれば、正義の神様は、叫び求める選ばれた人たちのために、正しい裁きをしてくださらないことがあろうか、否、速やかに正しい裁きをしてくださる、ということです。やもめが3節で、「相手を裁いて、わたしを守ってください」と言った言葉は、厳密に言えば、「相手を裁いて正義を確立してください」という言葉です。このように読み進めてきますと、今日のたとえが、単に、切に祈り求めることだけを教えているのではなく、祈り求めるべきは、正しい裁き、公正な裁判、神の正義であることが見えてきます。 旧約の時代から諸外国の支配を受け続けてきたイスラエルの人々は、神が約束された人の子・救い主を待ち侘びていました。いつか、イスラエルの国を建て直してくれる救い主が現れると、人々は待っていました。ただ、実際に神様が考える救い主の姿と、人々の待ち望む救い主の姿は違いましたが…。神様は、地上に救い主・人の子イエス様を遣わしてくださいました。人の子イエス様は、正しい裁きをなさる方です。神の国・神のご支配される国は始まりました。神の国の王なるイエス様は来られ、神の国は始まりました。イエス様は、神の国の福音を宣べ伝え、神様の御心を教え、何が本当に正しいことであるのか、神の国の真理を、神様の義を教え始めました。この正義の人の子・救い主は、王でありながら、一番低く小さな者となってくださいました。 イエス様は、神の国は、実にあなた方・私たちの間にあるのだと教えてくださいました。イエス様が来られたからには、神の国はイエス様を信じる者の間で始まっている。イエス様がおられる所で始まっている。けれども、その神の国は、まだ完成していません。完成は、人の子が再臨される時です。その時、神の裁きが行われ、人々は、イエス様を信じる人と信じない人に分けられます。弟子たちは、「主よ、それはどこで起こるのですか(ルカ17章37節)」と尋ねました。人の子の到来・主の再臨の時は、神様のみがご存じですが、確実に起こることです。 世界は、はるか昔から、ノアの時代も(17章26~27節)、ロトの時代も(17章28~29節)、人間の営みは変わっていません。でも、時代の時々で、人の間には、神から離れてしまった罪のために生じる不正、不道徳、自分勝手、貪り、敵意、暴力、搾取などなど…がはびこっています。そこに神がおられなくなってしまっている。天地万物命の創り主なる神様への畏れがなくなってしまっている。愛がなくなってしまっています。イエス様が来られて、本当の愛が示されて、十字架によって救いは確実なものになりましたが、まだまだ完成はしていません。人の子イエス様に反対する悪の勢力はあり、弟子たちは迫害を受けるようになり、世には、やはり罪による戦争がやみません。痛み、悲しみ、苦しむ人々が多くいます。正しい裁きがなされていません。この世に正しい裁きと神の正義が打ち立てられて、この世に神の国の愛と平安が満ちていくには、まだまだ時間がかかりそうです。神様、その時はいつでしょうか。 今日のたとえのやもめは、正義の裁きが行われることを求めました。たとえ不正な裁判官であっても、この人が裁判官である限り、必ず裁判をしてくれることを信じて、しつこく訴え続けました。ここに、やもめの信仰があります。今日、イエス様が弟子たちにたとえを話された目的は、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためです。絶えず祈り求めなければならないことは、正しい裁きがなされる神の国です。神の国と神の義です。神様の正義のご支配が広がっていくことです。でも、人は祈り求めているようで、なかなか真剣に求め続けられません。旧約時代から祈り求めていたイスラエルの人々も、何度も何度も神様から離れる不信仰に陥りました。祈る前に諦めてしまうことも多々あるでしょう。 イエス様は、8節後半で言いました。「しかし、人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見いだすだろうか。」将来の再臨の時のことだけではなく、今、イエス様がすでに来られて神の国が始まっている時代にあって、弟子たちや人々の間に信仰はあるのだろうか、と言われています。地上の人々は、神の正しい裁きがこの世に行われることを、本当に求めているのだろうか?ということです。裁き・裁判は原告がいなければ始まりません。原告が裁き主に対して、罪を、悪を裁いてください、正義を確立してください、私を守ってください、と訴え出なければ始まりません。神の時は確かに訪れます。でも、正しい神の裁きが速やかに行われますようにと、今日のやもめのように、しつこく訴え続ける信仰が求められています。イエス様のお話は、祈りから信仰へ移っています。 かつてユダヤ人は、日に3度の祈りが義務付けられていましたが、イエス様は、頻繁に父なる神様に祈っていました。祈りは神様との対話であり、霊的な呼吸でもあります。呼吸を止めれば命が危うくなるのと同じように、祈りを止めれば、信仰の命は止まってしまうでしょう。だからイエス様は、絶えず祈ることを私たちに教えます。イエス様ご自身、十字架を前にして、御心がなりますようにと祈り続けておられました。宣教の初めからずっと、御心がなり、御国が来ますようにと祈り続け、その祈りを弟子たちに、私たちに教えてくださいました。 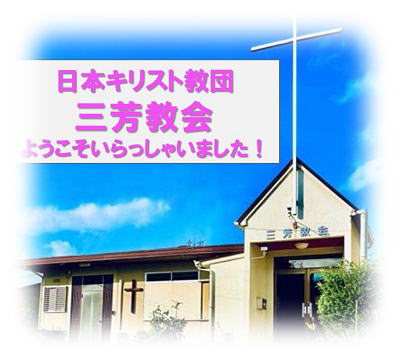 この世の現実を見れば、神を恐れず人を人とも思わない罪に満ちていて、神の正義とは正反対に向かっているようで、時に諦めてしまいそうになります。でも神様は、この世界に福音を届けようとしておられ、神の国を完成へ向けておられます。地上に、イエス様の体なる教会を建ててくださいました。私たちもイエス様の弟子として、僕として、祈り続けていきます。この世界のために、人々のために、一つひとつ具体的な祈りを重ねつつ、そうして、神様のご支配がこの世に広がりゆきますように、御心がなりますように、御国が来ますようにと祈り続けます。 この世の現実を見れば、神を恐れず人を人とも思わない罪に満ちていて、神の正義とは正反対に向かっているようで、時に諦めてしまいそうになります。でも神様は、この世界に福音を届けようとしておられ、神の国を完成へ向けておられます。地上に、イエス様の体なる教会を建ててくださいました。私たちもイエス様の弟子として、僕として、祈り続けていきます。この世界のために、人々のために、一つひとつ具体的な祈りを重ねつつ、そうして、神様のご支配がこの世に広がりゆきますように、御心がなりますように、御国が来ますようにと祈り続けます。神様は、私たちが信仰を失うことなく、祈り求めることを願っておられます。私たちには、信仰がなくならないようにと取りなし祈ってくださっているイエス様が共におられます。人の子・救い主イエス様を目の前に仰ぎながら、私たち共にその方と歩みながら、神の国と神の義を求める祈りに生きていきましょう。この世を精一杯に生きて、やがて迎える死を超えてなお、神の永遠の愛と命と平安に生かされていくという確かな救いを前にして、信仰に生きていきましょう。 |
| 三芳教会 渡邊典子牧師 (わたなべ のりこ) |
![]()
| 今月のみことば | H O M E |